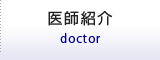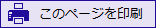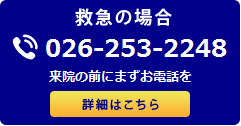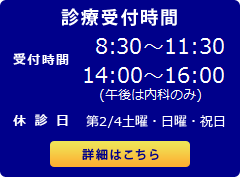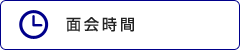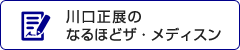No.206 episode 3
2013/01/18
大輔が病棟に到着すると
近藤さんは気管内挿管され、人工呼吸器が装着されていた
どうやら自発呼吸は戻っているようであったが、意識がない
挿管をしてくれたであろう当直医はすでに病棟にはいない
看護師も病室を巡回しているのか、ナースステーションには誰もいなかった
「ドルミカムのせいだ」
大輔は自分の医療行為が招いた重大な結果に、今更ながら体がふるえた
ドルミカム、一般名ミダゾラムは
その添付文書によると、保険適応が 「麻酔前投薬、集中治療室における人工呼吸中の鎮静」 となっていて、不隠の鎮静に対する適応などない
しかも、麻酔前投薬における使用量は
「 1回体重 1kg当たり 0.08から 0.1mg」とあるから、近藤さんの場合、 6.8から 8.5mg、すなわち 1アンプル 10mgは明らかに過剰である
さらに、あまり時間を置かないで 2回目を注射している
すべてが掟破りだった
大輔は、部屋まわりをしている看護師を見つけると、状況をたずねた
「ラウンドの時、近藤さんが呼吸をしていないことに気付きました」
「でも脈は触れていたので、アンビューを揉みながら当直の小栗先生に連絡したんです」
呼吸停止の原因を知らない彼女は、冷静に、そう答えた
- 無呼吸による低酸素血症が、どのくらいの時間続いていたのだろう?
- 意識は果たして戻るのだろうか?
- このまま、近藤さんが植物状態になってしまったらどうしよう
- 患者さんの家族には、一体どう説明すればよいのか?
- 医療過誤で訴えられるのだろうか?
- いや、それより、自分は刑事被告人となるのだろうか?
さまざまな考えが、次から次へと大輔の頭の中を巡った
と同時に、今までの失敗の数々が脳裏をかすめる
- 喘息の既往のある患者に造影剤を使ってCTをおこなった所、喘息重積状態になってしまったこと
- 意識障害で搬送された患者の呼吸が安定していたので、挿管しないで頭部CT室に搬送したところ、CT中に呼吸が停止したこと
など など
混乱した頭で彼が出した結論は
「医者なんかにならなければ良かった」
と
「とりあえず家族に事実を話して、謝らなければ」
であった
大輔が、カルテの家族欄に 「妻」 と書かれた携帯に電話をすると
近藤さんの奥さんは、 30分ほどして病棟に現れた
大輔は
「不隠状態を抑えるために鎮静薬を、添付文書にない方法で使用したこと」
「鎮静には成功したが、おそらく、鎮静薬が過剰であったことが原因で無呼吸となったこと」
「無呼吸で低酸素脳症を起こしたものと思われ、意識が戻らず、植物状態になってしまうかも知れないこと」
ほぼ、ありのままを説明した
それをじっと聞いていた白髪の夫人は、はじめ、少し驚いた様子だった
しかし、彼女は、少し間を置いたあとで
「先生、主人は自分の好きなように生きてきた人です。 いくら私が言ってもお酒をやめようとはしませんでした。 いずれにしても、これから末期癌の苦しみが待っていたのです。 意識がないことは、きっと夫に天が与えてくれた、せめてもの優しさなのだと思います。 先生のせいではありません。 どうか先生、御自分を責めないで下さい。 これがあの人の運命だったのです。」
と、笑みを浮かべながら、しかし大輔の顔は見ないで、あたかも自分自身に言って聞かせるように語った
大輔が夫人を見ると、その端正な顔に、一筋の涙が頬を伝っていた
- つづく かもしれない -
この物語は全くのフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません